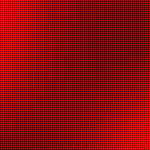最終更新日 2025年7月8日 by amcgsr
「障がいがあっても、夢を諦める必要なんてない。」
今ならそう自信を持って言えます。でも、就活を始めた頃の私は、不安でいっぱいでした。こんにちは、佐藤花子です。今日は、私の就活体験を通じて、障がい者雇用の現実と可能性についてお話しします。
私が初めて就活を意識したのは大学3年生の冬。周りの友達が次々と説明会に参加し始める中、生まれつき肢体不自由がある私は、自問自答の日々を過ごしていました。「私にも働けるチャンスはあるのだろうか」「どんな仕事ならできるんだろう」。
当時描いていた障がい者雇用のイメージは、正直あまり明るいものではありませんでした。単純作業ばかりで、能力を活かせる仕事はないのではないか。そんな思い込みが私を縛っていたのです。
でも、実際に就活を始めてみると、その現実は私の想像とは大きく異なっていました。様々な挑戦と出会いを経て、今の私があります。この記事を読んでいるあなたも、きっと不安を抱えているかもしれません。でも、大丈夫。私の経験が、あなたの道しるべになれば幸いです。
目次
障がい者雇用って? 私の就活スタート
新たな可能性との出会い
就活を始めたばかりの頃、私は障がい者雇用についてほとんど知識がありませんでした。転機となったのは、大学のキャリアセンターで偶然手に取った障がい者向けの就職情報誌でした。
その雑誌には、様々な業界で活躍する障がいのある方々の姿が紹介されていたんです。ITエンジニア、デザイナー、営業職など、私が想像もしていなかった職種で働く先輩たちの姿に、胸が高鳴りました。
「障がいは個性の一つ。それを強みに変えて働いている人たちがたくさんいるんだ」
この気づきは、私の視野を大きく広げてくれました。
就活支援サービスとの出会い
新たな可能性に気づいた私は、さっそく障がい者向けの就活支援サービスに登録しました。ここでの経験が、私の就活に大きな転機をもたらしたんです。
主な支援内容:
- 個別カウンセリング:自分の強みや適性を客観的に分析
- 業界研究セミナー:様々な業界の現状や求人傾向を学ぶ
- 模擬面接:実践的なトレーニングで面接スキルを磨く
- 障がい者雇用に積極的な企業との交流会
これらのサポートを受けることで、私の中にあった「できない」という思い込みが少しずつ解消されていきました。特に、実際に働いている先輩たちの体験談を聞けたことは大きな励みになりました。
私の障がいと向き合う
就活を進める中で、改めて自分の障がいと向き合う機会も増えました。特に印象に残っているのは、就活支援サービスのカウンセラーとの対話です。
カウンセラー:「花子さんの障がいは、どんな場面で困難を感じますか?」
私:「長時間の立ち仕事や、細かい手作業が苦手です。」
カウンセラー:「では、逆に花子さんの強みは何だと思いますか?」
私:「う〜ん、そうですね…」
この問いかけをきっかけに、私は自分の強みを深く考えるようになりました。障がいがあるからこそ培ってきた工夫する力、周りとコミュニケーションを取る力。それらが私の強みなんだと気づいたのです。
| 私の特性 | 仕事への活かし方 |
|---|---|
| 工夫する力 | 業務の効率化、新しいアイデアの提案 |
| コミュニケーション力 | チームワーク、顧客対応 |
| 忍耐力 | 長期的なプロジェクトへの取り組み |
| 細やかな観察力 | 品質管理、データ分析 |
| 多様性への理解 | インクルーシブな職場環境づくり |
この気づきは、その後の就活に大きな自信をもたらしてくれました。自分の障がいを隠すのではなく、それを含めた全人格で勝負する。そう決意したのです。
葛藤と挑戦の日々 – 私の就活体験記
履歴書作成でぶつかった壁
就活が本格的に始まり、最初の大きな壁が履歴書作成でした。特に「自己PR」の欄を埋めるのに、何日も悩みました。
主な悩みポイント:
- 障がいのことを書くべきか、書かないべきか
- 書くとしたら、どこまで詳しく書くべきか
- 障がいをポジティブに表現するにはどうすればいいか
これらの疑問が頭の中をぐるぐる回っていました。結局、私は障がいについて正直に書くことにしました。それは単なる事実の記載ではなく、障がいと共に生きてきた経験から得た強みを伝えるチャンスだと捉えたのです。
例えば、こんな風に書きました:
私には生まれつき肢体不自由がありますが、それゆえに培った「工夫する力」が私の強みです。日常生活の中で常に効率的な方法を考え実践してきた経験は、業務改善やプロセス最適化にも活かせると考えています。また、様々な支援を受けてきた経験から、チームワークの重要性と多様性の価値を深く理解しています。この自己PRを書き上げたとき、不思議と心が軽くなりました。自分の障がいを隠すのではなく、それを含めた全人格で勝負する。そう決意したのです。
面接での緊張と不安
履歴書選考を通過し、いよいよ面接。最初の面接前夜は、緊張で眠れませんでした。
不安要素:
- 質問にうまく答えられるだろうか
- 車椅子のまま面接室に入っても大丈夫だろうか
- 障がいについて、どんな質問をされるだろう
- 面接官は障がいに対してどんな印象を持つだろうか
不安は尽きませんでしたが、深呼吸をして自分に言い聞かせました。「大丈夫、自分の言葉で正直に話せばいい」と。
実際の面接では、予想外の質問もありました:
- 「障がいによって仕事に支障が出ることはありますか?」
- 「職場でのサポートで必要なことは何ですか?」
- 「あなたの障がいを、会社にとってのプラスに変えられると思いますか?」
これらの質問に対し、準備していた答えを述べるだけでなく、自分の言葉で率直に応答しました。例えば、「障がいがあるからこそ、多様性の重要性を実感しています。それを活かして、より包括的な職場環境づくりに貢献できると考えています」と伝えました。
面接を重ねるごとに、少しずつ自信がついていきました。自分の経験を語ることで、面接官の方々も真剣に耳を傾けてくれる。そんな手応えを感じられるようになったのです。
何度も訪れた挫折と、それでも諦めなかった理由
就活の道のりは決して平坦ではありませんでした。何度も書類選考で落とされ、面接で不採用を告げられました。特に辛かったのは、最終面接まで進んだにも関わらず不採用だった時。「やっぱり私には無理なんじゃないか」と、何度も挫折しそうになりました。
でも、そんな時に支えになったのが、就活仲間の存在でした。障がい者向け就活イベントで知り合った仲間たちと、LINEグループを作って情報交換をしていました。
仲間との活動内容:
- お互いの面接経験を共有
- 落ち込んだ時の励まし合い
- 業界情報の交換
- 模擬面接の実施
この仲間たちの存在が、私に「諦めないで」と語りかけてくれました。みんな同じように悩み、頑張っている。その思いが、私の原動力になったのです。
また、あん福祉会のスタッフ募集についてのような情報を見つけた時も、「こんな素敵な職場で働けたら」と、新たな希望が湧いてきました。あん福祉会のような場所で、自分の経験を活かせる仕事があるかもしれない。そう思うと、もう一度頑張ろうという気持ちになれたのです。
就活の過程で、私は自分自身の成長も実感していました。最初は自信がなかった自己PRも、面接を重ねるごとに堂々と語れるようになっていったのです。
そして、掴んだ仕事 – 私の「今」
今の仕事内容とやりがい
紆余曲折を経て、私は現在、IT企業のウェブアクセシビリティコンサルタントとして働いています。主な仕事内容は以下の通りです:
- ウェブサイトのアクセシビリティ診断
- 様々な障がいを持つユーザーの視点でウェブサイトを検証
- 問題点の洗い出しとレポート作成
- 改善提案の作成と提示
- クライアントに対して具体的な改善案を提案
- コスト面も考慮した現実的なソリューションの提示
- クライアント企業向けの研修実施
- アクセシビリティの重要性に関する啓発セミナーの実施
- 開発者向けの技術的なワークショップの開催
この仕事の最大のやりがいは、自分の経験を直接活かせること。障がい当事者として培ってきた視点が、仕事の質を高めることにつながっているんです。
例えば、ある大手ECサイトのアクセシビリティ改善プロジェクトでは、私自身の使用経験をもとに具体的な改善案を提示しました。
改善提案の一例:
- ナビゲーションメニューのキーボード操作性の向上
- 商品画像の代替テキストの充実
- フォームのエラーメッセージの明確化
その結果、クライアントから「ユーザー視点の提案で非常に参考になった」と高評価をいただきました。さらに、改善後のサイトでは、障がいのあるユーザーからの問い合わせが減少し、購買率も向上したという報告を受けました。
このように、自分の仕事が直接的に社会のバリアフリー化につながっていることを実感できるのは、この上ない喜びです。
職場環境と理解ある仲間たち
現在の職場環境は、私の障がいに対して非常に理解があります。入社時には、オフィスのレイアウトを一部変更してくれたり、必要な支援機器を用意してくれたりしました。
具体的な配慮の例:
- デスクの高さ調整
- 音声認識ソフトウェアの導入
- フレックスタイム制の適用(通院のため)
同僚たちも、自然に声をかけてくれます。
「花子さん、この資料の文字サイズ、大きくした方がいいですか?」
「移動の時、手伝えることあったら言ってくださいね」
こうした何気ない気遣いが、働きやすさにつながっています。また、私の障がいについてオープンに質問してくれる同僚もいて、そういった対話を通じて職場全体の障がい理解が深まっていくのを感じます。
就職して変わったこと、そして変わらないこと
就職して大きく変わったのは、自己肯定感です。「自分にも社会に貢献できることがある」という実感が、日々の生活に自信をもたらしてくれました。
具体的な変化:
- 経済的自立:自分で稼いだお金で生活することの喜び
- 社会とのつながり:仕事を通じて様々な人と出会い、視野が広がった
- 時間の使い方:規則正しい生活リズムが確立された
- 目標設定:キャリアプランを考えるようになった
一方で、変わらないのは挑戦する姿勢です。就職はゴールではなく、新たなスタートライン。今でも新しいプロジェクトや、より難しい業務に挑戦し続けています。
最近の挑戦例:
- 社内でのアクセシビリティ啓発活動のリーダーに
- 業界カンファレンスでの登壇発表
- 新入社員の教育・メンタリング
これらの経験を通じて、私自身も成長を続けています。障がいがあることで諦めていた夢も、少しずつ実現できるようになってきました。
障がい者雇用のリアル – 私が伝えたいこと
障がい者雇用の現状
まず、障がい者雇用の現状について、いくつかの統計データを見てみましょう。
graph TD
A[障がい者雇用の現状 2023年] --> B[法定雇用率]
A --> C[実雇用率]
A --> D[雇用者数]
B --> E[民間企業: 2.3%]
B --> F[国・地方公共団体: 2.6%]
C --> G[民間企業: 2.24%]
C --> H[国・地方公共団体: 2.85%]
D --> I[約60万人]これらの数字を見ると、障がい者雇用は着実に進んでいるように見えます。実際、私が就職活動をしていた5年前と比べても、募集枠は確実に増えています。
しかし、数字の裏には様々な課題が隠れています。
障がい者雇用のメリットとデメリット
実際に働いてみて感じた、障がい者雇用のメリットとデメリットを共有します。
メリット:
- 自分の経験を活かせる機会が多い
- 多様性のある職場環境で働ける
- 法定雇用率の関係で、採用のチャンスが比較的多い
- 企業側の理解や配慮が得られやすい
デメリット:
- 業種や職種が限定される場合がある
- キャリアアップの道筋が見えにくいことも
- 周囲の理解不足による摩擦が生じることがある
- 能力以上に配慮されすぎて、チャレンジの機会を逃すことも
これらのメリット・デメリットは、個人の経験や勤務先によって大きく異なります。重要なのは、自分に合った環境を見つけることです。
まだまだある課題と、これからの展望
障がい者雇用は確実に進んでいますが、まだまだ課題も多いのが現状です。
現在の主な課題:
- 職場のバリアフリー化の遅れ
- 障がいへの理解不足
- 柔軟な働き方の選択肢の少なさ
- 精神障害・発達障害に対する配慮の不足
- 中小企業での雇用促進
これらの課題に対して、私たち当事者が声を上げ続けることが重要だと考えています。同時に、企業側の努力も不可欠です。
障がい者雇用の歴史と展望:
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1960 | 身体障害者雇用促進法制定 |
| 1976 | 法定雇用率制度の導入 |
| 1987 | 障害者雇用促進法に改称、知的障害者も対象に |
| 2006 | 精神障害者も雇用率の算定対象に |
| 2016 | 障害者差別解消法施行 |
| 2024 | 民間企業の法定雇用率2.3%に |
| 未来 | さらなる雇用率の向上、質の改善 |
今後の展望として、テレワークの普及やAI技術の発展により、障がい者の就労機会はさらに広がると期待しています。例えば、音声認識技術の進歩は、聴覚障がいのある方の職域を大きく広げる可能性があります。
また、SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、インクルーシブな雇用は今後ますます重要視されるでしょう。企業にとっても、多様な人材の活用は競争力の向上につながります。
就活を始めるあなたへのメッセージ
最後に、これから就活を始める障がいのあるみなさんへ、私からのメッセージです。
- 自分の障がいを隠さず、強みに変える勇気を持とう
- 支援サービスを積極的に活用しよう
- 仲間を作り、情報交換や励まし合いをしよう
- 挫折しても諦めないで。必ず道は開ける
- 自分の権利を知り、必要な配慮を求めよう
そして、何より大切なのは自分を信じること。あなたにしかできない仕事が、必ずあるはずです。
障がい者雇用Q&A
Q1: 障がいのことを面接で話すべきですか?
A1: はい、オープンに話すことをおすすめします。ただし、自分の強みや工夫についても同時に伝えましょう。
Q2: 職場での合理的配慮について、どう相談すればいいですか?
A2: 入社前や試用期間中に、人事部門と具体的に相談することが大切です。必要な配慮を明確に伝えましょう。
Q3: 障がい者枠で入社すると、キャリアアップが難しいのでは?
A3: 必ずしもそうではありません。自分の能力を示し、積極的にチャレンジする姿勢が大切です。
まとめ
私の就活体験から得た最大の学びは、「障がいは個性であり、強みになりうる」ということです。最初は不安でいっぱいだった就活でしたが、今では自分の障がいを含めた全人格で仕事に取り組めています。
確かに、障がいがあっても自分らしく働ける未来は、着実に近づいています。でも、それは私たち一人一人の努力と、周囲の理解があってこそ実現するものです。
key takeaways:
- 障がいは決してデメリットだけではない
- 適切な支援と環境があれば、能力を最大限に発揮できる
- 就活は自己理解と成長の機会
- 多様性を認め合う社会づくりに、私たちも貢献できる
これから就活を始める皆さん、自分の可能性を信じて頑張ってください。どんな困難があっても、必ず道は開けます。私は皆さんの挑戦を、心から応援しています!
そして、この記事を読んでくださった企業の方々にも、ぜひ障がい者雇用の意義を考えていただければと思います。多様な人材が活躍できる職場は、きっと創造性と生産性の高い素晴らしい環境になるはずです。
一緒に、誰もが自分らしく働ける社会を作っていきましょう。